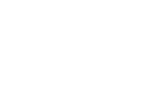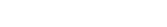在学生インタビュー:4年生・大学院生編
4 年生と大学院生の学生に、研究室での生活や研究の醍醐味について聞きました!
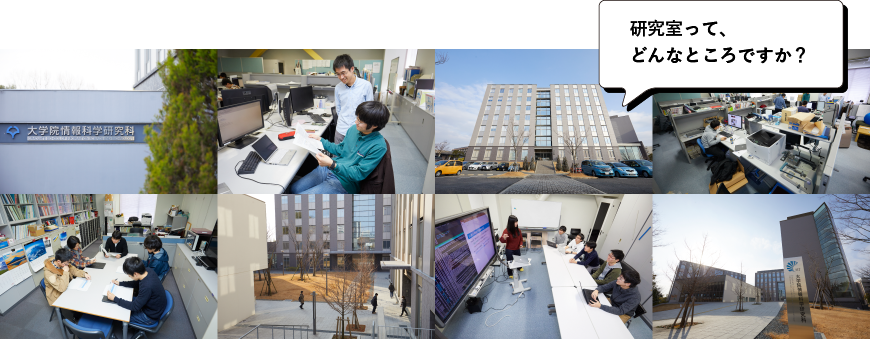
4年生 土居 真之さんソフトウェア設計学講座 楠本研究室
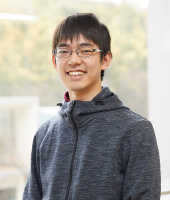
研究室に配属されたときは、自分専用にハイスペックのパソコンをポンと支給されて、充実した研究環境に「すごいな」と驚きました。計算能力が高くて作業をサクサクこなせます。週日はほぼ毎日、朝9時ごろから夕方5時ごろまで研究室で作業をして、疲れたら研究室のみんなでわいわい話をしてという生活リズムで、研究室は設備の整った家みたいな居心地の良さです。
現在は、プログラムの内部構造をすっきりさせる「リファクタリング」という分野の研究に取り組んでいます。
修士課程1年 佐々木 美和さんソフトウェア設計学講座 楠本研究室
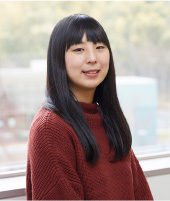
大学生活は高校時代までに比べて自由度が高いです。その分、自己管理が大事なのですが。
私の場合は、研究室に来るのは週に3回くらいで、研究の状況を打ち合わせて、夕方には帰宅します。大学と自宅、双方をつなぐ環境が整っているので、自宅でも研究を進められます。大学には先生に相談に来る感じです。
研究室によって違いますが、研究室に籠もって作業したい人、自宅で自分のペースで進めたい人、どちらでも選べるのが良いところです。
社会に出た時に、これを深く研究したという自分だけの何か誇れるもの身につけておきたいと思って、大学院に進みました。今は、世界中のプログラマーに使われているツールであるGit の機能を進化させる研究をしています。自分が改良したものを世界中の人が使ってくれて、それに対してフィードバックがあると、自分の手で何かものを便利にしたという実感があり、そこが魅力です。
修士課程1年 山本 瑶司さん情報流通プラットフォーム講座 長谷川研究室

3年生の夏に大学院入試を受けて、飛び級で研究室に入りました。1年早く進学して社会に出るのを1年早められれば、可能性がより広がるかもしれないと考えたからです。
毎朝9時半ごろ研究室に来て5時ぐらいまで研究し、週に1回は指導教官の先生と個別にミーティングがあります。研究室に出てくれば、自宅で作業するのと違ってメリハリを付けられるし、すぐに指導教官の先生に相談できるので、大学に来て作業するようにしています。
3年生までの学部時代は基礎的な知識や技術をつける時期。研究室に入れば、問題を解決するためにさまざまな知識を動員して立ち向かい、うまく結果を出し、それを上手に伝える方法まで自分で組み立てなければいけません。総合的な力が必要になってきます。研究室に入ってからのこの一連の流れの中に、学部時代に身につけた知識が生きていると実感しているところです。
IoT(Internet-of-Things:もののインターネット)時代を支える、次世代のネットワーク機構について研究しています。自分が頑張ればその分返ってくる研究室で、例えば、大学院に入ってすぐにカナダ・トロントで開かれた国際会議で発表するチャンスを得ることができました。今はまだ小さなことですが、世界で誰も手がけていなかったことを自分が切り開き、成果を論文にして世界中の人に見てもらえるのが研究の醍醐味だと思います。
博士課程2年 光成 浩一さん集積システム設計学講座 橋本研究室
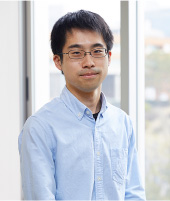
大学に入った時から大学院には行こうと思っていて、早く本格的に研究を始めたかったので、飛び級で大学院に進みました。カメラの映像から物体を見つけるシステムを手がけています。運転支援システムなどで、世界中の研究者が競争している分野です。省電力、小さな計算パワーでもスマートに高速で処理できて高い精度で物体を見分ける仕組みを研究しています。
研究室では、計算の方法を考えたり、プログラムを書いたりして検証を繰り返し、結果がまとまってきたら論文にして発表します。研究は指導教官の先生と相談しながら進め、学年が上がると同じ研究室の後輩たちの面倒を見たりもしています。
私の研究室では企業と共同研究をする機会もあり、ビジネスにも触れられます。自分の名前の入った特許もあります。
大学の授業で与えられる課題は答えがある程度見えていてそれをこなす感じのものも多いですが、研究はやってもうまくいかないかもしれない。でもチャレンジして未知の領域に挑んでいく面白さがあります。
(2018年1月19日・22日インタビュー)